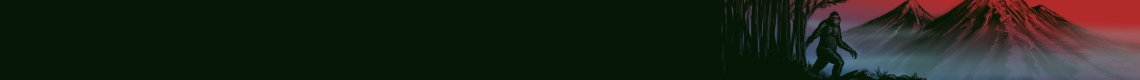--P1--
「ミスチル現象」とまで言われた94、95年の活躍は、96年に入っても衰えをみせなかった。年が明け、2月にリリースされた「名もなき詩」は、これまでにも増して、ピュアに相手と添い遂げようとする愛を描き、創意にみちた曲構成も新鮮で、 大ヒットを記録した。しかし頂点に立った者にしかわからない虚無感が、一方では忍び寄り始めていたのだ。
「百万枚セールスする曲を」と、そう夢を語っていた頃とは違ってきた。それが現実になり、出すシングル出すシングル、 それが普通になった。「でも、あいつはどこかで、何かを背負ってるようだった」(鈴木)。周囲は「音楽シーンの頂上」と言ったが、本人達がそこから見た景色は、何の感情も涌かない「無」であった。20代で成功を手に入れた桜井に対するマスコミの興味は、彼のプライベートな部分にも向けられた。しかし彼らは、休むより作り続けることで、それを解決していった。
『Atomic Heart』以降の活動が濃密過ぎて、気がつくと、丸2年アルバムを出していなかった。未収録のシングル曲が、多数存在していた。これらを軸に新曲も加えてレコーディングを始めたら、10曲や12曲では到底納まらない。そこで考えられたのが、傾向の違う二枚のアルバムを、同時に作っていくという方法論だ。その時、当初予定されたのは、アメリカやヨーロッパ、ジャマイカなども候補地に入れた、世界一周レコーディングだった。実に刺激的なアイテアではあったが、諸事情から収縮された形で実現され、東京・ニューヨーク・ロンドンをまわりながらのものとなった。
メンバーにはかねてから、再び訪れたい場所があった。4人の等身大のサウンドを得るためにも、そこは不可欠だったニューヨークの「ウォーター・フロント・スタジオ」である。しかも今回は、レニー・クラヴィッツのアナログ・サウンドの立役者、ヘンリー・ハッシュが直々に音作りに加わってくれる。滞在は4ヵ月に及び、やがてアルバム全体をひとつの流れに繋げてまとめる、コンセプト・アルバムの構想が生まれた。冒頭の「手紙」という曲に結末があり、そこに至る経過を、以下に続く楽曲によって解き明かしていくような、そんな構成となった。ヘンリー・ハッシュの音作りは厳しいまでに徹底し、演奏する4人に集中力を要求した。桜井の書く詞には、例えば愛ならば、希望だけでなく絶望も同居させた。それが当時の彼にとって、もっともリアリティのあることだった。
--P2--
日本から持っていった楽曲の中に「花」があった。痩せた音なら、歌の世界観も痩せてしまいそうなこの曲が、自信に満ちた演奏とスタジオの鳴りの良さで、見事に仕上がった。「思い描いていた以上の大きな道が見えた」(中川)。この曲を先行シングルに、遂に問題作『深海』は完成した。普段3分間のポップスを気軽に聴いている耳には、とてもヘヴィな内容だった。「ミスチル・ファンであり続けていくための踏み絵」とまで言われた。しかしセールスは、トリプル・ミリオンを突破。アルバムの完成にともなって計画されたツアーは、「リグレス・オア・プログレス」、つまり「退化か進化か?」と題されて、 「深海』をまるまる演奏するという、今までにない試みを含むものとなった。しかもアリーナ・クラスを55公演という、観客動員も破格なものだった。しかし、スケジュールも内容もメンバーにはキツかった。「あのアルバムを作っていた頃の内側に籠もっていく感覚が、毎回蘇ったから」(田原)。
もう1枚、平行して準備されていたアルバムは『BOLERO」と名付けられた。あのラベルの「ボレロ」になぞらえて、少しずつ、徐々に拓いていく、という、そんな想いを込めてのものだった。「深海」がアナログ・サウンドを究めた内容だったのに較べ、こちらはデジタルなものへのアプローチも旺盛で、つまり2枚のアルバムを同時に作る際に、基本コンセプトとして最初にあったのがこのことだったのだろう。これまでに出された5枚ものミリオン・ヒットを含み、どうしてもベスト・アルバム的に受け取られる面もあったが、新たに書き下ろされた6曲は、決してそれらに依存しないタフな輝きを持っていた。「タイムマシーンに乗って」や「傘の下の君に告ぐ」などは、攻めに転じたイメージだった。かくしてこの2年半の活動が、このアルバムによって、完結することとなった。97年に入ると、ツアーのファイナルとして初のドーム公演も行われる。
やがてミスチル解散説が囁かれ始める。区切りをつけたら「1年くらい休養しよう」という計画なら、当初からあった。しかし解散など、毛頭考えていなかった。「バンドが解散するのは才能がないか、仲が悪いか、解散するしか話題がない時だけ」。その時、桜井は、こんなウィットのある言葉で、世間の噂を笑い飛ばしてみせた。
--P3--
97年3月31日。「恵比寿ガーデンホール」周辺は、ものものしい雰囲気だった。ファン1000人を集めての、シークレット・ライヴが行われようとしていたからだ。しかし会場内は、いたってリラックスしていた。彼らはお酒を飲みながら、十数曲を演奏した。このスペシャルな企画は、ツアーの打ち上げの意味を持っていて、「また会えるかな」を最後に、4人はステージを去っていった。
「ロック・バンドに有給休暇があったっていい」 (桜井)。実際、ここ2、3年、休み無く突っ走った。田原と中川は、運転免許を取得すべく、教習所に通った。鈴木の自宅の留守電には、大勢の友人から「飲もう」と誘いの連絡が入った。桜井は、さらに充実した曲作りの環境のため、最新コンピューター機材を購入し、まずそのマニュアルを読むことから始めた。 彼らはこうして、おのおのの休みに突入した。
中川と鈴木には、ある計画があった。「林英男」という名前のセッション・バンドを結成し、ライヴハウス・ツアーを行った。マイ・リトル・ラヴァーの藤井謙二と、デビュー当時から親交のあるザ・ピロウズの山中さわおが一緒だった。田原は人のライブを観たりゆっくりCDを聴いたり、普通の音楽ファンの生活をした。そうやって観に行ったひとつが、「林英男」だった。田原にとってそれは、ミスチルというものを客観的に捉えるいい機会となった。
彼らはオフに入ったが、映像関連の新譜リリースは続いた。ビデオ・クリップ集や先のツアーのドキュメントなどが出された。桜井の曲作りは、時間を見つけては続いていた。今までのようにギターで作るものもあったが、サンプリング音源を土台にループ作りから発想していくものもあり、それらはそのまま、このバンドに新しい風を送ることにもなった。休みとはいえ、4人で集まることもあった。サッカーや野球を楽しみ、そして行きつけのお店で、ばったり出会ったりもした。そんな時、桜井はメンバーに、まるでタバコを一本勧めるかのように、出来立てのデモ・テープを聞かせた。彼の手元には、コンピューターの肩慣らし的に作った曲も、活動再開にあたり、指針になりそうな曲もあった。
--P4--
「ニシエヒガシエ」は前者、とはいえ、試みを越え、やがて見事に完成していったこの曲に、タイミングよくドラマ主題歌の話が舞い込む。結果、まずは楽曲だけの“復活”となった。この曲と「光の射す方へ」は、明らかにいままでと違うミスチルだ。複雑に絡まっていくループのリフと、それに触発された、まさに言葉の奔流のような歌詞。ちょうど宅録派ミュージシャンの音楽が注目を浴びた時期でもあったが、彼らの作品は音圧的にも上だった。
そして本格的に活動を再開したのは、休みからちょうど1年後、98年の4月だった。「久しぶりに音を出した時は、興奮したけど緊張した」(鈴木)というように、中学・高校の同級生から始まった彼らは、ここで再びフレッシュな気持ちでバンドに向かえる状態になった。構えずにレコーディングが始まった。そして完全復活を遂げたのが、「終わりなき旅」の時である。 「閉ざされたドアの向こうに 新しい何かが待っている」。このフレーズが印象的だった。「このドアは自分の中にある、自分で自分を閉ざしてるドアなんです。だからそれを開けるのも自分自身」(桜井)。その後もレコーディングは、プライベート・スタジオで、まさに自宅で寛ぐような雰囲気の中で行われた。桜井がアレンジも含め煮詰めて作ったもの以外は、誰かの閃きから曲の方向性を探し、それが連鎖反応でまた新たなアイデアを生んでいく、といった、まさにバンド・セッションを優先した作り方だった。休み中、サーフィンの腕を磨いた桜井の作る曲は、何かに逆らったり、ではなく、そこに身を任し同調してくような、そんな作風も身につけていた。「曲を作るのも波を捉えるのも似てる。大きな波じゃなくても、小さな波にはそれなりの“乗り方”がある」(桜井)。こうして、自らのバンドの力量を、再度、掘り起こしたアルバムは、「DISCOVERY」 と命名された。「深海』の頃の桜井は、もういない。30代に突入した彼らは、むしろ身軽になっていた。
ツアーも同様だった。旅の荷物は少なめ、いや、最低限だった。それはまず、何よりも「音楽」。巨大スクリーンの演出などを排して、でも今まで通り、アリーナ規模の会場を涌かせてみせた。スタジオでレコーディング中に、4人で演奏する。 その姿こそ真のミスター・チルドレンなんだと再認識した彼ら。だったらそれに一番近い形を、ファンの人達にも見てもらいたい。このツアー・コンセプトはここから生まれた。ところで彼らには、まだやってないことが、ひとつあった。それはライヴ・アルバムを出すことだ。この時の42公演の中の一夜、札幌での公演が、「1/42」のタイトルでリリースされた。
--P5--
2000年を迎えての彼らは、熱心なファン達が待ち望んでいた、ストレートなラブ・バラード「口笛」でスタートした。散歩中にふと口をついて出てきたメロディを書き留めたような、そんなこの歌の佇まいは、今現在に至るまでの彼らの活動を、 まさに象徴していた。イントロから、メロディに深みをもたらす小林武史のキーボードが効いた音作りも、ギターサウンドにこだわりをみせていたここ1、2年とは違っていた。この年の音楽界はバラード・ブームとなったが、その先鞭をつけたのがこの楽曲ではなかろうか。
このように、『DISCOVERY」でバンドの絆を確かめあった4人は、さらに伸び伸びと次のレコーディングへと向かっていった 「前作も決め事なしにやったけど、自由にバンド・サウンドをやろう、ということ自体が決め事になってた」(桜井)という、この言葉がすべてを物語っている。
シーンの動向を気にしながら、つまり音楽の中から音楽を捻り出す窮屈さではなく、日常の様々な楽しみの横に、さり気なく音楽があるといった、そんなスタンスが確認される。たとえばこんなことがあった。4人はスタッフとともに、「ジュビケン」というサッカーチームを組んでいる。このチームが大活躍して、テレビのサッカー番組でゴールシーンだけが編集されて放映されたら、そこにはどんなカッコいい音楽が流れるのか? こんな発想から作られた曲がある。実際その時、彼らはスタジオのリビングでそんな番組を楽しみ、その気分のまま楽器を手にして、その高揚感のまま、それを楽曲にしていった。
そこに名曲を作るためのセオリーなどなかった。不確定な要素を、あえてスタジオの中に持ち込むことすらあったのだ。“2000年ミスター・チルドレン・ダーツの旅”である。楽曲のテンポ感というのは、スタジオでは3桁の数字で表される。 それを投げたダーツによって決定したりもした。コード進行を、あみだくじで決めた曲もあった。別に考えることをやめたわけじゃない。そうやって、ひとつの楽曲に対しての可能性を増やし、試していった、ということだ。後日、そんな話をメディアに向けて披露した彼らは、「え、ダーツ!?」と、キョトンとする相手の姿を楽しんでいた。
--P6--
レコーディング環境は、ますます良くなっていた。1時間使用しただけで目の玉が飛び出るくらいの経費がかかる街中のスタジオではなく、彼らのプライベート・スタジオ、そして、残念ながら閉鎖された「ウォーター・フロント・スタジオ」のヴィンテージ器材を譲り受けて完成した、所属事務所のニューヨーク・スタジオもオープンした。これらを存分に使えたのだ。日本でセッションしたものをニューヨークに持って行って、再び日本でレコーディング。この往復によって、楽曲が揃えられていった。そのニューヨークでの様子は、99年の暮れ、スペースシャワーのスペシャル番組として放映された。この番組とともにいったん完成したのが「Hallelujah」だったが、それをさらに別のヴァージョンで年明けに再び試してみた。こういうことが可能なレコーディングだったのだ。
ソングライターとしての桜井のスタンスも変わっていった。「DISCOVERY」ではバンド・サウンドを優先したため、個人的な歌はそぐわなかった。しかし今回は、その制約もなかった。喋り言葉の語感を、より大胆にメロディに乗せてみた曲もあった。21世紀への望みを、胸を張り高らかにうたいあげるものもあった。愛しい人への想いも、ストレートに歌ったものもあった。小林武史のピアノと対話するかのようなバラードも出来上がった。アルバムは、リリースを待つばかりとなった。 時間はあっという間に経過して、前作から1年7ヵ月、「Q」がリリースされる。こうして彼らの歴史を追っ掛けているが、現在に近づくほど、活動方針はゆったりしたものになっていることがわかる。そして最新アルバムは、今までのどのアルバムとも違う、もっともリラックスした彼らの姿を捉えたものだった。アルバムに続いてツアーがスタートした。よく「最新アルバムを引っ提げて」と表現されるが、このツアーこそ、まさにそれを引っ提げてのものだった。これまでの楽曲も、もちろん演奏されたのだが、後半の盛り上がりどころを、すべて『Q』の中の曲でまかなった。音楽以外のことを排除した前回のツアーとは違って、スクリーンなどの演出も、必要とあらば加えられたものとなった。
この7月は、初のベスト・アルバムのリリースにあわせて、95年の「空」以来の野外コンサートが実現する。30代の油の乗り切った時期へと突入していく彼らが、来年どんなオリジナル・アルバムを発表するのかが楽しみだ。まだ気が早いが、あの「Hallelujah」をも遙か上空に突き抜けた、文字通りの新境地を期待したいものだ。