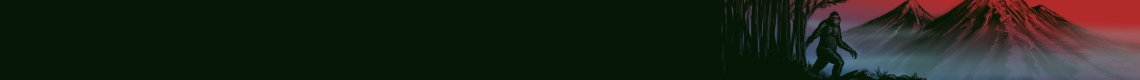--前言--
実はこのベスト・アルバムは、シングルの「口笛」が出た頃に、いったんは企画されたものだった。当時彼らは、暇な時間をみつけては、ファースト・アルバムから順に、過去の作品を聴き直していたのだ。しかしその時は、「どの曲を選べはいいのか?」も、「いま、ベストを出す意義」もわからないまま、見送られることとなった。巷でベスト盤が、ブームのようになっていたこともあった。便乗していると受け取られても、なんか違う。気持ちが変わっていったのは、昨年アルバム『Q』が完成して、ツアーで全国を回っている時だったと、そう桜井は言う。
「ホントに幅広い年齢層の人達が観に来てくれた。それこそ中学生もいたし、子供連れのお母さんもいた。そして、みんなそれぞれにぼくらとの出会いがあって、“『Kind of Love』こそがミスター・チルドレンだ”って人もいるし、“いや、『深海』以降でしょ”って人もいるんだと思う。でもここらで、アルバムごとの区切られた評価じゃなくて、それらを全部まとめて、 ポンとひとつの“ミスター・チルドレン像”みたいなものに出来ないだろうかと、そう考えた」
だからこの場合、音楽活動に区切りをつけよう、というニュアンスとは、ちょっと違う。そもそもここのところ、彼らのやることは、1年微妙にズレているのだ。デビュー8年目の昨年に出たアルバムのタイトルが『Q』(キュー=9)で、9年目にこうしてベストが出る。普通なら、区切りのいい、丸10年の記念となる来年だろう。そう。来年はどうなってしまうのだろうか? 「実は、次にやるべきことが、明確に見えてる。新しい曲も出来てるし、バンド・セッションの手応えも充分なんです。早くそっちに取りかかりたい気分」
比較的前期に思い入れのある人は敢えて後期を、逆の人は逆を、そんな優先順位で聴いてみるのはどうだろう。そしてこのバンドの本質はなんら変わってないことを、聴き終えた時、発見する事だろう。
――――――筆.小貫信昭
--P1--
バンドには二種類ある。作ったバンドと作られたバンドだ。しかし成り立ちがどうあれ、バンドは作り続けていかなければ先へ進めない。このベスト・アルバムの主人公、ミスター・チルドレンがそうだったように。
彼らが生まれたのは、1969年(桜井だけ早生まれで70年)。あのウッドストック・フェスティヴァルが開かれ、ロックにとってエポック・メイキングといわれた年だった。田原健一と中川敬輔と鈴木英哉は、東京都狛江市の同じ中学校の出身である。桜井和寿は、東京都練馬区の出身。この4人は、多感なティーンを似た環境、つまり東京とはいえ、まだ自然が多く残る地域で過ごした。その後同じ高校で、桜井と田原と中川が出会う。
彼らがバンドを組みたいと思ったのは必然だった。世の中が、BOØWYやレベッカの活躍に端を発するバンド・ブームだったからだ。中学の文化祭で、田原と中川は同級生が演奏する姿に感激。高校に進学したら、バンドをやろうと、卒業を期に楽器を購入する。この時すでに、田原がギターで中川がベースと、まだバンドもないのに担当を決めていたのが面白い。音楽に関して早熟だったのは鈴木で、すでに中学生の頃からギターやドラムを演奏していた。家の近くに多摩川の河川敷があり、何ならドラムの練習場にもなった。
姉のギターを借りて、見よう見まねで弾いたところ、その姉にいたく褒められたことから音楽に積極的になっていく桜井も、高校は絶対に「軽音楽クラブ」のあるところ(で、共学のところ!)と考えていた。「どうせやるなら絶対にプロでやりたい」。この年代の男子にしては、しっかりした考えの持ち主で、甲斐バンドや浜田省吾のレコードに合わせて歌っているうち、歌うことの喜びも涌いてきていた。
高校に入ると、軽音で出会った仲間と最初のバンドが結成される。女性キーボード奏者も加わって、当初は「Beatnik」 と名乗り、他人の曲のコピーはそこそこに、すぐオリジナル作りに励んだ。「最初は満足に演奏出来なかったけど、オリジナルなら、自分達のやれる範囲でやればいい」(田原)。プロ指向ゆえのオリジナル重視、とは別に、そんな切実な理由もあったのだ。まもなく桜井は、曲作りの才能を発揮し始める。ガールフレンドを讃えた爽やかなラブ・ソングも作ったが、 社会の授業でベルリンの壁崩壊の意味を知るや、そんなテーマの歌も作った。
--P2--
田原はリトル・リーグで活躍してきた経緯から、いったんはバンドを諦め野球部に所属するが、彼がテレキャスター・モデルを所有してることを知った桜井が、ある日こう告げる。「明日から、バットをギターに持ちかえろ!」。新入生の時に最初に仲良くなった中川は、程なく出席日数が減少していった。でも桜井は、中川を失いたくなかった。学食の自販機でホット・レモネードを奢り、こう言った。「学校はやめても、バンドは続けよう!」。苦心したのはドラム探しだ。なかなか続く人が見つからない。しょうがないから、桜井がドラムを叩きながら歌う時期が続いた。でも彼らの「プロになる」という意志は、周囲の好反応もあり、萎えることはなかった。そもそも尾崎豊は、十代ですでにプロとして認められていたし、若すぎるとも思わなかった。オーディションに応募すると、いつも楽曲審査でいいところまで行った。ライヴハウスにも、ちょくちょく出始めていた。
そんなある日のこと。吉祥寺のライヴハウスで一緒になった幾つかのバンドの中に、田原と中川の中学校の同級生の顔があった。当時「フェアリーランド」という名のバンドに所属していた鈴木である。3人で、彼を誘った。高校卒業という岐路のなかで、メンバー間で進路が話し合われ、桜井、田原、中川が残った。そこに新加入の鈴木と、この4人で固まった。その後間もなく、彼らはめでたく、当時プロへの登竜門だった、「SDオーディション」の決勝大会に進出する。しかし合格はならなかった。当時は 「The WALLS」と名乗っていたのだが、文字通り、壁にぶちあたってしまったのだった。このオーディションにはユニコーンがゲスト出演しており、そのカラフルで力強い音楽性には、大いに刺激を受けた。
オーディション終了後、グループ名を「ミスター・チルドレン」に改名し、年が変わり89年からは、この名前で活動することを決意する。いつも4人が集まっては四方山話をしていたファミレスのテーブルの上で、いくつかの候補の中から選ばれた名前だ。それまでの彼らは、辻仁成率いるエコーズに影響され、問題意識を歌ったナンバーも多かった。しかし、 「本来自分の中にないものを、無理してつくろってたのかもしれない」(桜井)と言う通り、さらに広い視野で音楽に向かっていく意志が、この改名とともに確認された。渋谷のライヴハウス「ラ・ママ」のオーディションに合格し、出演出来ることになったのもラッキーだった。
--P3--
「ラ・ママ」で着実に動員を増やしつつあった彼らは、関係者の目にとまり、デビューの誘いもいくつか舞い込むようになる。当時はまだ、ホコ天やイカ天の影響によるアマチュア・バンドの“デビュー・ブーム”が続いていたからだ。しかし彼らは慎重だった。そして91年。転機がやってくる。自ら望んで3ヵ月間の活動休止を申し出た後、桜井は新たな気持ちでの曲作りに励み、バンドは音楽性を広げ、ライヴハウスに戻ってきた。大方の意見は、「前の方が良かった」だった(この時4人はドドンパ風の楽曲まで手がけていた)。しかし、トイズ・ファクトリーの稲葉は「今の君たちにこそ可能性を感じる」と言った。当時、色々と世話をしてくれた人達のつてもあり、ジュン・スカイ・ウォーカーズが所属する「バッド・ミュージック」への所属も決まった。プロへのお膳立てが整った。4人はジュンスカのライヴのオープニング・アクトを努め、プロのバンドが成すべきことを学んだ。さらに大きな出来事は、プロデューサー小林武史との出会いである。小林は桑田佳祐のソロや小泉今日子の「あなたに会えてよかった」の作曲者として知られていたが、4人を手がけるにあたり、まず「バンド・ ブームに対して“カウンター・カルチャー”となるべき方策」を練った。重要なのは、たとえアーティスト写真一枚でも疎かにしないことだ。そのディレクションは、ユーミンやフリッパーズ・ギターを手掛け、CDジャケットをアートにまで押し上げたと言われた、コンテムポラリー・プロダクションの信藤三雄が手掛けることとなった。
そして4人と小林との曲作りのコラボレーションが、彼の家で始まる。こと作品作りに関しては、ここまで挫折もなくやってきた桜井は、ここでプロの凄さと厳しさを知る。小林は楽曲に対して忌憚のない意見を述べ、曲の構成法や詞の在り方を、どんどん手直ししていった。92年に出た7曲入りのデビュー・アルバム「EVERYTHING」は、勢いの良さが魅力な部分もあるものの、曲の完成度の確かさこそが印象的な内容だった。反応の良さから、「君がいた夏」がシングル・ カットされた。
彼らがデビューした頃といえば、チェッカーズなど大物バンドの解散が相次ぎ、通信カラオケの普及で「歌」への需要がさらに高まった時期だった。ドラマ主題歌からミリオン・セラーが生まれ始め、300万枚のセールスも夢ではなく、日本人アーティストがアリーナ公演を可能にした頃でもあった。
--P4--
もし第一線で活躍しようとするなら、音楽シーンの巨大化への対応は、避けて通れないものだ。そんな時、彼らが最初に行ったのは、曲作りを確固たるものにすることだった。小林と桜井がアイデアをぶつけ、楽曲を練り上げることに集中したアルバム、『Kind of Love」が完成した。技術革新も著しかった。コンピューター上に生楽器の音まで取り込めるシステムが開発され、いち早く彼らは、それを活用した。アルバムは、名曲揃いだった。しかしバンドの作品集というより、小林と桜井、二人のタッグによるところが大きい。
ミスチルはバンドなんだ。その原点に立ち戻る必要があった。次の「Versus』は、楽器おのおのの音に、さらなる生命力を吹き込むべく、ニューヨークの「ウォーター・フロント・スタジオ」が使用された。レニー・クラウヴィッツがアナログ・ロック復興の拠点としていた場所だ。結果、楽曲とバンドの骨格が、タイトル通り対峙した作品となり、雑誌のネクスト・ブレイク候補に、彼らの名前があがり始めた。まだデビュー2年。
それと並行して、「幅広く認められる曲」を目指し奮闘したのが桜井だ。「確かによく言っていた。必ず100万枚セールスする曲を作るって」(鈴木)。最初にタイアップがついたのは、お菓子のCFで流れた「Replay」だ。手応えは上々。その4 ヵ月後、彼らにとって、初のドラマ主題歌となったのが、「CROSS ROAD」だった。桜井が捜し求めていた、人を感動へ誘う黄金律のようなものを、ついにこの曲で見つけたのだ。バンドをやる楽しさだけでは、ロック幻想のぬるま湯のままだ。 「姿勢」は残せても「楽曲」は残せない。かといって、バンドをないがしろにしてまでセールスに走っても、4人でいる存在理由がなくなる。しかし彼らには、そんな心配はなかった。ツアーの動員が順調な中、「CROSS ROAD」は演歌のように売れた。チャートのベスト5には一度も入らなかったが、発売22週目には、遂に初のミリオンを達成したのだ。
--P5--
「CROSS ROAD」のヒットにより、「青春の甘酸っぱいラブ・ソングを歌わせたら定評あるバンド」と認知された彼ら。 さらに「innocent world」のヒットが続き、人気は不動のものに。しかしこの曲は、バンドの節目となる内容だった。というのも、それまでの曲は「より幅広く受け入れられる事」を目指し、登場人物やシチュエーションがドラマチックに整えられたものが大半だった。しかし「innocent world」は、詞の中に“ミスター・マイセルフ”という言葉が出てくるように、桜井個人が自らの内面をぶちまけた歌だった。彼は「このあたりから、どんどん自我を解放していく」(桜井)ことになり、しかしそれがより多くの人達に支持されたことで、前代未聞の快進撃が始まるのだ。「もっと巨大な怪獣になりたいという欲求」 (桜井)が、次なる目標へと駆り立てる。その結果完成したのが、あの「Atomic Heart」だ。バンドの生音にデジタルなサウンドを大胆にぶつけていくデジ・ロックの手法と、遺伝子レベルまで遡って愛を考察しようという歌世界が合体した、今までになく実験的で、なおかつ新たなポップ観をまとった作品となった。
バンドを巡る状況も急変した。より腰を据えた活動を目指し、所属事務所を現在のウーロン舎に移したのもこの時期だ。そして、先を見据えた小林武史のプロデュース・ワークも、最高潮へ達していく。彼はこの『Atomic Heart」というアルバムを軸に、内容のまったく異なるふたつのツアー、“TOUR INNOCENT WORLD"と"TOUR Atomic Heart"を、 途切れる事なく連続して敢行するアイデアを考える。肉体的パフォーマンスを重視する前者、巨大セットと最新テクノロジーの中にバンドを同居させようとする後者。その対比。さらにバンドの急成長を、ドキュメンタリー映画に記録する。かくして94年から95年にかけてのミスチルは、彼らの人生の中で、もっとも多忙な日々を迎える事となる。
しかしツアーがメインとはいえ、創作意欲は衰えない。その最初のツアー中にリリースされたのが「Tomorrow never knows」で、まさにツアー先のホテルで書かれた曲だった。生きていくことそのものを歌ったようで、バンドが置かれている状況をリアルに歌っているようにも聞こえるこのバラードには、大物バンドとしての風格すら備わってきた。
--P6--
当初、そのカップリング用に考えられていた「everybody goes ~秩序のない現代にドロップキック~」を、新しいシングルとして1ヵ月後にリリースしようと思ったのは、ツアーをしながらツアーでさらに盛り上がる曲を作るという、1分1秒たりとも無駄にしない、あの当時の彼らの実に濃密なクリエイティヴィティのなせる技だった。こうして桜井の曲づくりのタブーが、 ますます無くなっていく。そして、バンドを始めたのなら、ひとつの到達点である初の武道館公演(いきなり2日間だった) も、この年の暮れに実現する。しかしそのすぐ後に“TOUR Atomic Heart"という巨大なものが待っていたため、まさに通過点という感覚しかなかった。「innocent world」は、レコード大賞を受賞。ミスチルは、こうして94年の顔となった。
クリスマスも正月も殆ど休まず、新しい年がやってくる。明けて7日には、新しいツアーがスタートした。トータル72面のキューブ・スクリーンが積み上げられ、「Atomic Heart」というアルバムが、立体的に語りかけた。観る者の予想を遥かに越えた、音と光が織りなす一大エンターテインメントだった。肥大の一途を辿っていたバンドへの期待感に、こうして見事に応えてみせたのだ。
チャリティにも積極的になっていったのがこの時期でもあった。桑田佳祐から誘いを受けて、AAA (Act Against AIDS) のコンサートに参加。その桑田と桜井がデュエットした「奇跡の地球」は、AAAの新たなキャンペーン・ソングとなり、「LIVE UFO」のステージは、ロック・オペラ仕立てで、ストーンズやディランなど、黄金時代のロック・スタンダードを次々と熱唱していく構成。しかし、こうして走り抜けてきた日々を、ここらで振り返る時期がやってきた。ドキュメンタリー映画【es】は、新たな海外ロケを含み、そしてテーマ曲の完成とともにロードショー公開された。夏には野外イベント「空」で、 実りの多かったこれらの日々が、感謝を込めて、夏の夜空に、そしてファンの元へと還されたのだった。